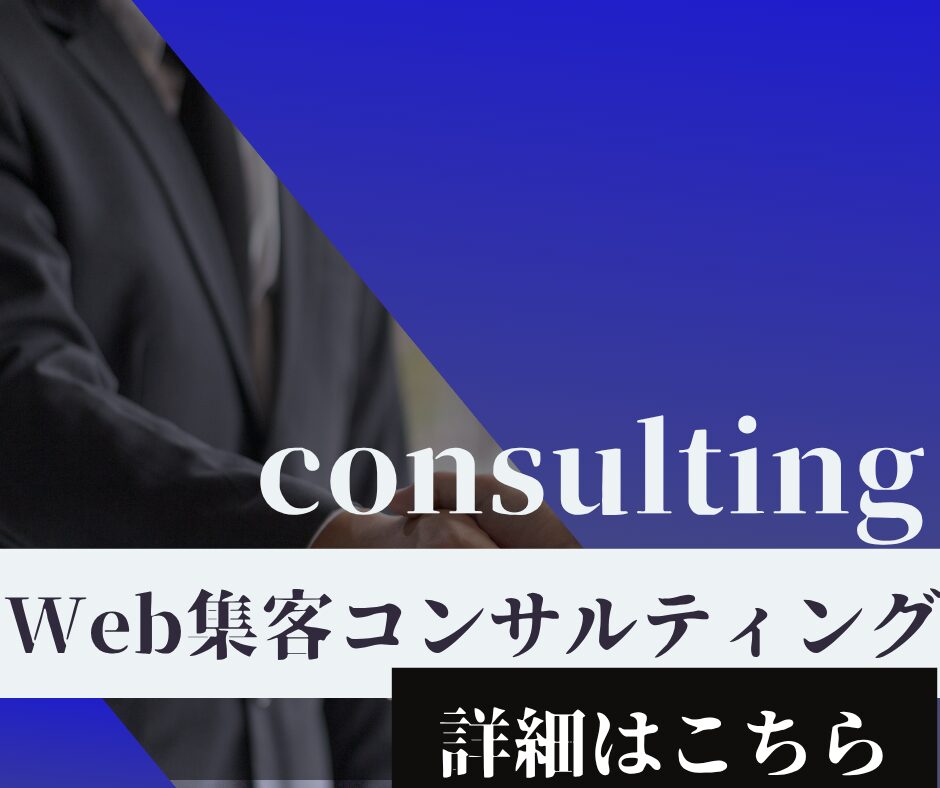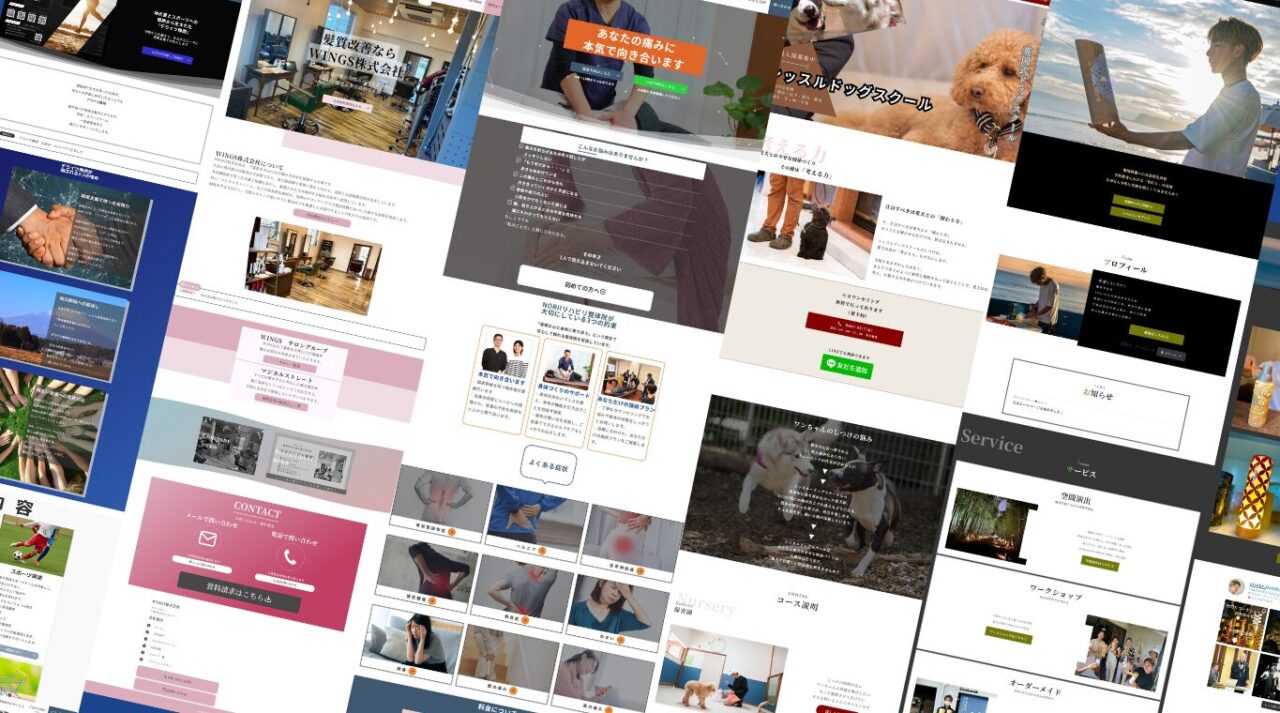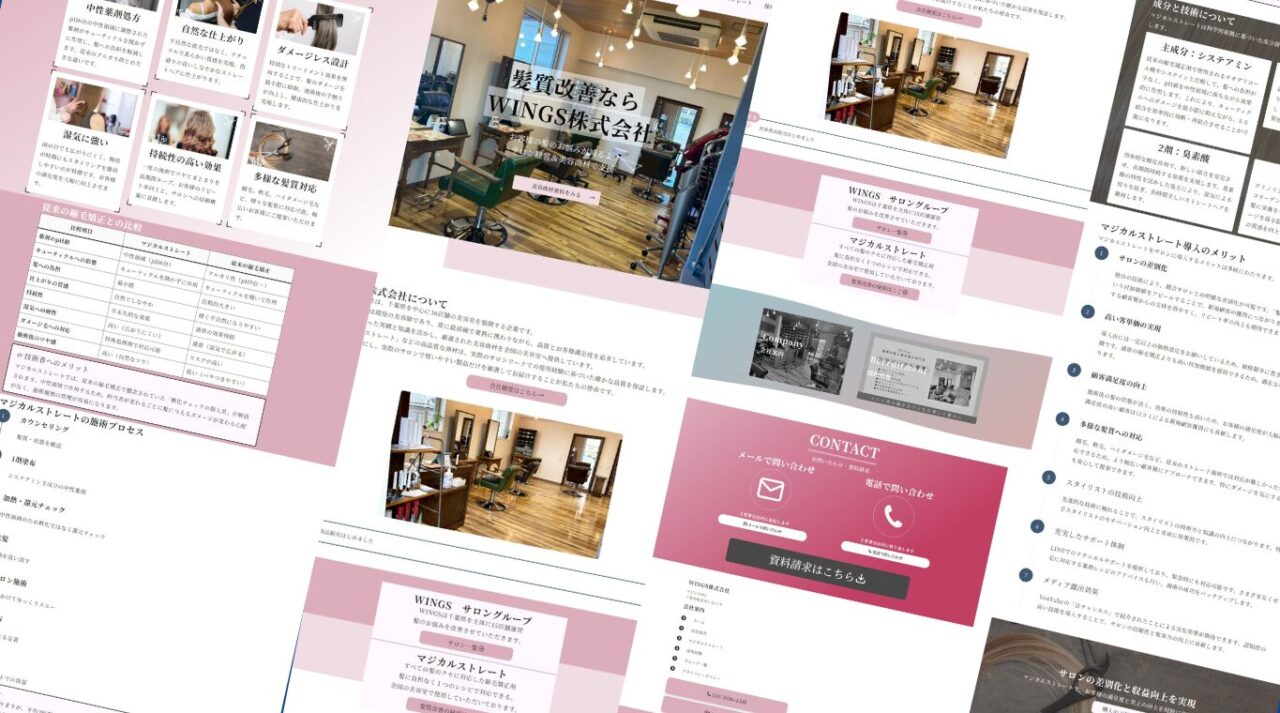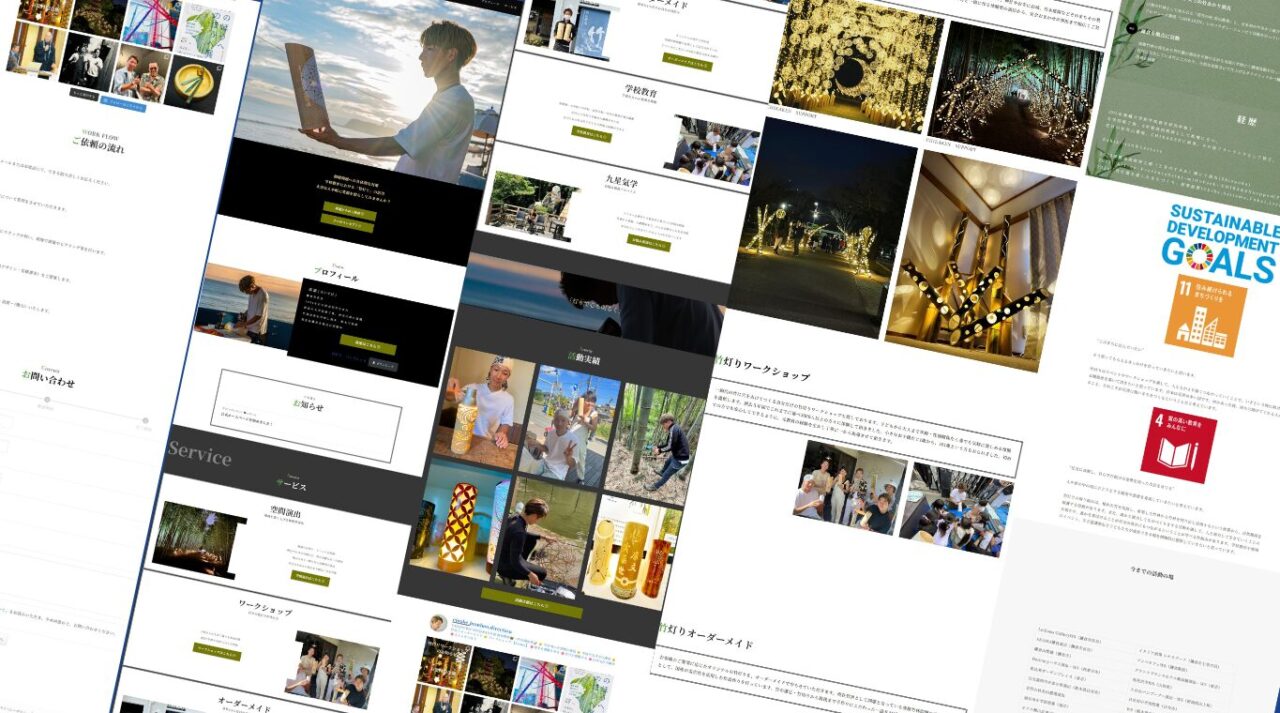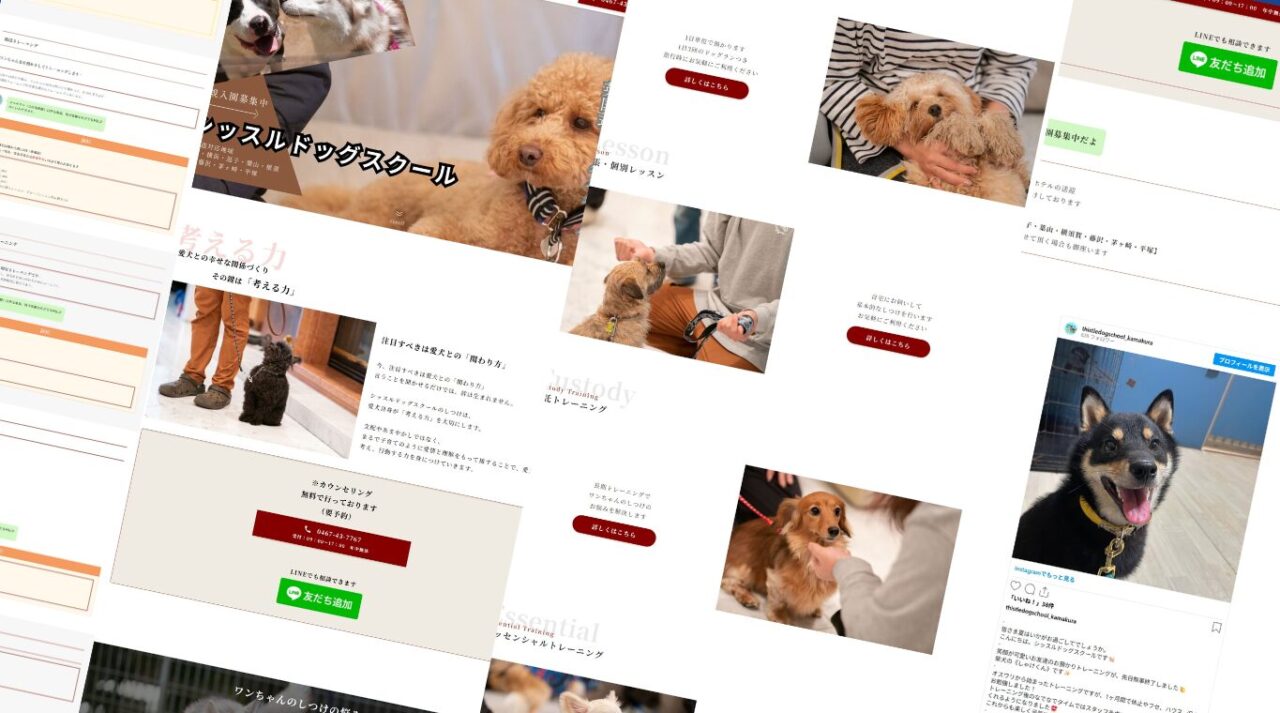「なぜあの商品は売れるのに、うちの商品は売れないんだろう?」
こんな悩みを抱えているマーケティング担当者は多いんじゃないでしょうか。
実は、商品が売れるかどうかって、お客さんの「意識」よりも「無意識」に働きかけられているかどうかで決まるんです。
この記事では、顧客心理の研究で明らかになった「人がつい買ってしまうメカニズム」と、その心理を活用した実践的なマーケティング手法をご紹介します。
アンケートやお客様の声に頼ったマーケティングで失敗してきた方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
人が「つい買ってしまう」理由は無意識にある
購買行動の95%は無意識レベルで決まっている
驚くかもしれませんが、私たちが日常で行う選択の大半は、実は無意識のうちに決定されているんですよね。
脳科学とマーケティングを組み合わせた「ニューロマーケティング」の研究によると、人間の購買判断の約95%は、本人が気づかないレベルで脳が処理しているそうなんです。
つまり、「なぜこれを買ったのか」という質問に対する答えは、ほとんどの場合、後から脳が作り出した「もっともらしい理由」に過ぎないということなんですね。
じゃあ、これがマーケティングにどう関係するのか?
例えば、スーパーマーケットでの買い物を思い浮かべてください。
カゴに商品を入れた理由を一つひとつ明確に説明できますか?
おそらく難しいと思います。
「なんとなく目に入ったから」「いつもここにあるから」という感覚的な理由が大半なんですよね。
【実例】小売店の「ゴールデンゾーン」が証明する無意識の力
ここで興味深い事実をお話しします。
小売業界では、陳列棚の中で最も見やすく手に取りやすい高さ(床から約75〜135cm)を「ゴールデンゾーン」と呼んでいて、この位置だけで什器全体の売上の8〜9割を占めるんです。
つまり、同じ商品でも置く場所によって売上が大きく変わるということ。
でも面白いのは、お客さんに「なぜこの商品を選んだんですか?」と聞いても、「棚の位置が良かったから」とは答えないんですよね。
「品質が良さそうだったから」「価格が手頃だったから」って答えるんです。
これって何を意味するかというと、お客さん自身も「なぜ買ったのか」の本当の理由を理解していないということなんです。
参考データ出典: 東芝テック株式会社
「お客様の声」が実は一番信用できない理由
アンケート結果と実際の購買行動にはギャップがある
マーケティングでよくある失敗パターンがこれです。
よくある失敗例:
- 顧客アンケートで「商品を選んだ理由」を聞く
- 「品質がいいから」「価格が適正だから」という回答が多い
- 品質改善と価格訴求に予算を投入する
- でも売上は伸びない…
なぜこんなことが起きるのか?
答えは簡単。
お客さんが答える「理由」は、実際の購買を決めた要因ではなく、購入後に自分を納得させるために作った説明だからなんですね。
【実データ】美容院の集客調査で分かった意外な真実
実際の調査データを見てみましょう。
美容室利用者3,600名を対象にした調査では、リピートしたい理由として「料金」が最も多く506件、次いで「接客」396件、「技術」321件、「立地」283件という結果が出ています。
この数字だけ見ると「料金と接客が重要なんだ」と思いますよね。
でも、別の調査では美容室を選ぶ決め手として最も多かったのが「家や職場から近い」という立地条件だったんです。
つまり、お客さんは実際には「近くて便利だから」という理由で選んでいるのに、アンケートでは「技術力」や「接客」など、もっともらしい理由を答えている可能性が高いんですよね。
【参考データ出典】
ホットペッパービューティーアカデミー
HAIRLOG SPECIAL
顧客が「つい買ってしまう」仕組みの作り方
じゃあ、どうすれば無意識レベルで選ばれる商品・サービスになれるのでしょうか?
ステップ1:無意識を動かす「感情設計」
人は理屈で考える前に、感覚で「いいな」「欲しいな」と感じます。この最初の感情を生み出す設計が何より重要なんですね。
感情を動かす具体的施策:
①アクセスのしやすさ(心理的・物理的) 実店舗なら入り口の開放感、ECサイトなら最初の3秒で目に入る情報。「ちょっと見てみようかな」と思わせる敷居の低さが決め手になります。
②視覚的な見つけやすさ ゴールデンゾーン(床から75〜135cm、または110〜140cm)に主力商品を配置すると、視認率が上がり売上の8割以上を占めるという業界データがあります。探す手間は購買意欲を削ぎます。
③五感への働きかけ パン屋の焼きたての香り、アパレルショップの心地よいBGM、化粧品の高級感あるテクスチャー。論理では説明できないけど「なんかいい」と感じさせる要素を設計してください。
ステップ2:論理的な「納得材料」を用意する
感情で「欲しい」と思ったあと、人は必ず理性で「本当に買っていいのか?」と自問します。
このとき、背中を押してくれる論理的な説明が必要になるんですね。
納得材料の具体例:
- 商品スペックの詳細説明
- 第三者機関の認証や受賞歴
- 具体的な数値データ(「満足度95%」「3000人が愛用」など)
- 返金保証や無料お試し期間
これらは「買う決断」をするためではなく、「買った決断を正当化する」ための材料なんです。
順番を間違えないように注意。
ステップ3:購入後の「正当化」をサポート
買ったあとに「いい買い物をした」と思ってもらうことも、実はマーケティングの一部です。
購入後フォローの例:
- 「この商品を選んだあなたは賢い選択をしました」というメッセージ
- 商品の活用法や上級者向けの使い方の提供
- 購入者限定コミュニティへの招待
こうした施策により、お客さんは友人に商品を勧めるときや、次回購入を検討するときに、ポジティブな「購入理由」を語れるようになります。
無意識マーケティングを実践する具体的施策
ECサイトでの実践例
感情を動かす施策:
- ファーストビューで高品質な商品画像
- 読み込み速度の最適化(3秒以内)
- シンプルで迷わないUI設計
納得材料の提供:
- 商品説明の充実(スペック、素材、製造過程)
- ユーザーレビューの表示
- 配送情報や返品ポリシーの明記
実店舗での実践例
感情を動かす施策:
- 入りやすい店構え(ガラス張り、オープンエントランス)
- 主力商品を目線の高さ(110〜140cm)に配置し、売上の8割を占めるゴールデンラインを活用
- 清潔感と適度な賑わい感の演出
納得材料の提供:
- 商品POPでの機能説明
- スタッフによる丁寧な商品説明
- 試用・試食の機会提供
よくある質問(FAQ)
- Q無意識マーケティングは洗脳や騙しではないですか?
- A
無意識マーケティングは、お客さんが本来求めているものとスムーズに出会えるようサポートする手法です。必要のないものを押し付けるのではなく、潜在的なニーズと商品をマッチングさせるのが目的です。
- Qアンケートは全く意味がないということですか?
- A
そんなことはありません。ただし、「なぜ買ったか」ではなく「商品の使用感」「改善してほしい点」など、実体験に基づく回答を集めるべきです。購買動機は行動データで分析し、商品改善はアンケートで行う、という使い分けが大切です。
- Q小規模ビジネスでも実践できますか?
- A
むしろ小規模だからこそ効果的です。大がかりな広告予算がなくても、店舗レイアウトの工夫、商品配置の最適化、接客トークの改善など、コストをかけずにできる施策はたくさんありますよ。
まとめ:感情が最初、理屈はあとで
ここまで読んでいただいて、マーケティングに対する見方が少し変わったんじゃないでしょうか?
重要ポイントのおさらい:
- 購買の95%は無意識で決まる → お客様の言葉より行動データを信じる
- 感情が先、理屈は後 → まず「いいな」と感じてもらい、その後で納得材料を提供
- 購入理由は後付け → アンケートの「選んだ理由」を戦略の軸にしてはいけない
- ゴールデンゾーンの活用 → 什器の売上の8〜9割を占める重要エリアを戦略的に使う
マーケティングの成功って、結局のところ「お客さんが無意識に感じる快適さ」をどれだけ設計できるかにかかっているんですよね。
論理的な商品説明や機能アピールも大切です。でもそれは、感情的に「欲しい」と思ってもらったあとに効いてくるもの。
この順番を間違えなければ、きっとあなたのマーケティングも大きく変わるはずです。
今日から「お客さんは何に無意識に反応しているか?」という視点で、自社の商品・サービスを見直してみてください。